循環器内科
循環器内科の診療
狭心症・心筋梗塞、心不全、弁膜症、不整脈などの心臓の病気や、肺高血圧や動脈瘤、動脈硬化など血管の病気の診療を行います。
循環器疾患のリスクとなる生活習慣病(高血圧、脂質異常症、糖尿病など)の診療もおこなっています。
狭心症
動脈硬化や成人病などが原因で冠動脈の血流が低下すると、心臓が酸素不足に陥り、胸の痛み、圧迫感、絞扼(こうやく)感(しめつけられる感じ)などの胸部症状が現れます。これが狭心症の発作です。
最初のうちは、心臓がたくさんの酸素を必要とする運動時だけに症状が出ることが多く(労作性狭心症)、安静にすると治まることが多いのですが、病状が進行すると安静時にも症状が現れるようになります。
また、狭心症の中には、冠動脈に動脈硬化がなくても、冠動脈自体が痙攣(れん縮)し血流が悪くなり、狭心症のような症状が出る場合があります。このような状態を「冠れん縮性狭心症」といいます。特に夜間から朝方にかけて胸痛発作が出現し、「朝方に胸が痛くて目が覚めた」という患者さんが多くいらっしゃいます。胸部症状を自覚するときには、早めに検査を受けることが大切です。

主な症状
- 胸の痛み・圧迫感(特に心臓の位置)
- 痛みが左肩・腕・背中・顎に放散することがある
- 運動やストレスによる発作の増加
- 発作の際に冷や汗や吐き気を感じることがある
- 発作は通常数分で軽減するが、長引く場合は注意が必要
- 心電図異常
- 息苦しい
心筋梗塞
動脈硬化や粥腫(コレステロールのごみ)などで冠動脈の内腔が狭くなったところが破綻する(崩れる)と血液中の血小板が破綻した部位に血栓を作り血管内を詰まらせてしまいます。それにより心筋に血液中の酸素が供給されなくなり心筋がダメージを受ける心筋梗塞を発症します。梗塞とは細胞が壊死した状態であり、心筋細胞が壊死することを心筋梗塞といいます。
心筋梗塞になると心臓の収縮力が低下し、心不全を引き起こしたり、心臓破裂や死に致る不整脈を引き起こし、命にかかわる危険な状態となります。

主な症状
弁膜症
検診等で心臓に雑音や胸部レントゲンで心拡大を指摘された場合、労作時の呼吸困難、胸の痛み、下肢のむくみ、全身倦怠感などの症状が自覚された場合に疑われます。時に失神発作などで発見されることがあります。弁膜症の検査は心臓超音波を用いて診断に至ります。
治療は、軽症~中等症までは、薬物治療(利尿剤、降圧剤、心保護作用のある薬剤など)が中心となります。しかし、病状が進んでくると、徐々に心臓の筋肉や腎臓、肝臓の機能など全身の臓器を障害して、最終的には手術(外科的またはカテーテル術)が必要となる場合もあり早期の発見と治療が重要です。

主な症状
心不全
心不全は、心臓が十分な血液を全身に送り出せない状態を指します。この状態は、心臓の機能が低下することによって引き起こされ、様々な原因が考えられます。主な原因には、冠動脈疾患、高血圧、心筋症、弁膜症、心筋炎などがあります。心不全は、急性と慢性に分けられ、急性心不全は突然発症し、重症化しやすいです。
心不全の症状には、息切れ、疲れやすさ、むくみなどがありますが、症状は患者によって異なります。心不全は慢性的な疾患であり、長期的な管理が必要です。治療には、生活習慣の改善や薬物療法、場合によっては手術が含まれます。適切な管理を行うことで、生活の質を向上させ、合併症のリスクを減少させることが可能です。心不全は一般的に深刻な状態ですが、早期発見と適切な治療によって、症状の改善が期待できます。

主な症状
下肢閉塞性動脈硬化症
動脈硬化症とは「動脈が硬くなる」ことです。動脈が硬くなると血管の中が狭くなったり、詰まったりして虚血という危険な状態に陥ります。
血管の内側が狭くなると必要な酸素、栄養がいきわたらず、臓器や組織が正しく機能しなくなります。さらに血管が詰まると臓器や組織に血液が流れず、壊死してしまうこともありますので注意が必要です。

主な症状
- 足の痛み(特に歩行時に発生、間欠性跛行)
- むくみ
- 脚や足の冷感・しびれ
- 足の皮膚の色の変化(青白くなることがある)
- 傷が治りにくい・潰瘍ができやすい
- 足の筋力低下
- 運動後の疲労感
不整脈
心臓は通常1日約10万回程度、規則的に拍動して全身に血液を送っています。 不規則に心臓が動いてしまう状態や、正常な範囲を超えた心拍数になる状態を大きくまとめて不整脈と言います。多くは、自分の胸の鼓動を不快に感じる「動悸」や胸部不快感などの症状を伴いますがまれに無症状であったとしても命に関わるような危険なものも存在します。
不整脈には多くの種類があり、症状がひどくなければ治療せずに様子を見てよいものから、心房細動のような脳梗塞を引き起こす不整脈や失神や心不全をきたすような重篤な不整脈なども存在しているため、正しい診断と治療が必要です。
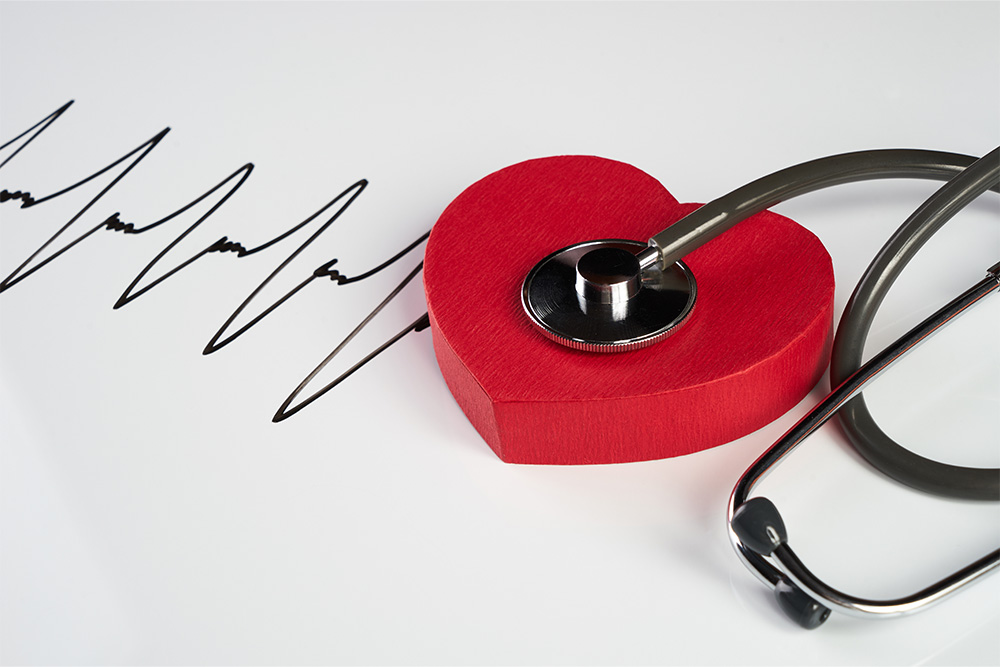
主な症状
肺塞栓症
心臓からの血液を肺に送り届ける肺動脈に、血液のかたまり(血栓)が詰まった状態を肺塞栓症といい、その結果、血流が滞って肺組織が壊死していく状態を肺梗塞といいます。原因としては、脚の静脈にできた血栓が心臓を介して肺に運ばれて起こることがほとんどで、長時間動かず同じ姿勢でいることで脚の静脈の血流が滞り、血栓ができてしまうと考えられています(このように脚に血栓ができた状態を深部静脈血栓症といいます)。一般的には、飛行機内のエコノミークラスのように狭くて動きづらい環境下で、長時間着席したままの状態でいることで生じることが多いため、エコノミークラス症候群とも呼ばれています。

主な症状
深部静脈血栓症
深部静脈血栓症とは、脚や骨盤などの深い場所にある静脈に血のかたまり(血栓)ができる病気です。この血栓が血管をふさいでしまうことで、腫れや痛みを引き起こします。
特に、長時間の座位(飛行機や車での長距離移動)、手術後の安静、下肢のけが、加齢、妊娠、経口避妊薬の使用、がんなどがリスク要因とされています。
もっとも注意が必要なのは、血栓が血流に乗って肺まで運ばれ、「肺塞栓症(はいそくせんしょう)」という命に関わる状態を引き起こす可能性があることです。早期発見と治療がとても重要です。

主な症状
- 片脚の腫れ
- 足の痛み
- 脚の熱感
- 皮膚の赤みや変色
- ふくらはぎの圧痛
- 静脈が浮き出て見えることも
慢性腎不全
慢性腎不全とは、腎臓の働きが徐々に低下し、長期間にわたって十分に機能しなくなった状態を指します。腎臓は、体の中の老廃物や余分な水分・塩分を尿として排出したり、血圧の調整、赤血球を作るホルモンの分泌など、生命維持に欠かせない重要な働きを担っています。
慢性腎不全では、これらの機能が少しずつ失われていき、体にさまざまな不調が現れるようになります。進行すると「慢性腎臓病(CKD)」と診断され、最終的には透析治療や腎移植が必要になることもあります。
原因には、高血圧や糖尿病、慢性糸球体腎炎などの病気が多く関係しています。初期には自覚症状がほとんどないため、定期的な血液検査や尿検査による早期発見がとても大切です。



